
プロフィール
――"軽量で熱伝導性の良い魔法銀"の基底鉱石、ボーキサイトの識者
明瞭快活なナルシスト。
ザントファルツの巫女たちに配給されている携帯用連絡端末のカメラ機能を用いて、何かにつけて自分を撮るのが趣味。また、学院で生まれ育ったオラクルにしては珍しく、教養や作法に関する知識がすっぽりと抜け落ちているような節がある。
彼女と出会った者の多くは、まず、彼女の美貌について言及するだろう。
華美に着飾ることはないが、整った顔立ちや佇まい、そしてスタイルにおいて、他者を魅了するに十分なカリスマを備えているようだ。また本人曰く、『完璧な造形を持つ、彫像の如き肉体を隠すことは美への冒涜』としており、『本来であれば服も着るべきでない』とのたまい、脚線の露出を好む。
とはいえ彼女は寒暖差に弱く、夜に冷え込むザントファルツでは、すぐに風邪をひいてしまうのだが。
ワガママな一面こそあるものの、コミュニケーション能力は高く、巫女寮の内外を問わず、多くの交友関係を持つ。巫女寮の寮長でもあるアリシアとは、学院時代からの旧知の友である。
「ブリジット。
あんた、食事をカメラで撮るなんて、ブ作法過ぎでしょ。」
「別にいいじゃない。この麗らかな一日を記録するほうが大事だわ。
そのために、私とこのデザートは、同じフレームに収まる必要があるのよ。
ほらアリシア、あなたも写真に入っていいわよ。手だけね。
…うん、撮れた。見てほらイイ感じ!」
「ほとんどあんたじゃん。」
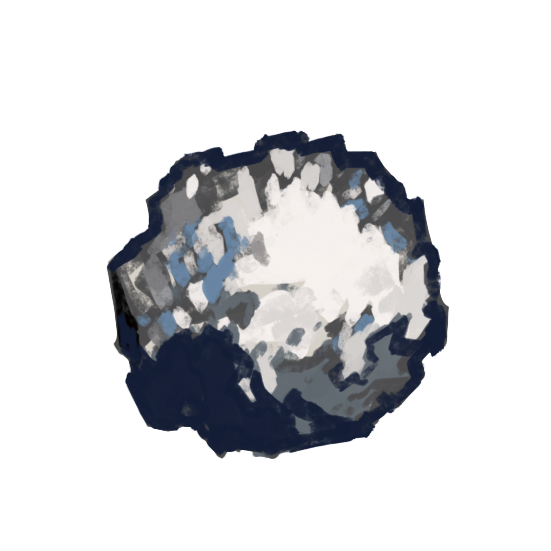
STORY
彼女の人間性に関する記述は以上の通りであり、他の巫女たちは彼女を「一貫性のあるキャラクターをしている」と評価するだろう。だが、彼女にとって自らの個性は「薄弱」と一蹴する他にない。
何せ、それらはすべて、紛い物なのだから。
彼女の精神的性質は、彼女が先天的に得た異界の知識のひとつ…"ある絵画"が持つ、膨大な量の情報によって形成されている。
緻密な芸術作品の完璧な記憶など、どうして"ひとりの人間"に為し得るだろうか。
その情報がすべて、多角的に、平行的に、余すところなく頭脳に収容され、それを描いた筆者の価値観、美観さえも、強制的に理解させられてしまうとしたら。
その影響を受けた後、その脳によって動かされる精神と肉体は、
果たして"ひとりの人間"と言えるのだろうか。
"芸術"。
このカテゴリの知識を授かった巫女の中には、その負荷によって、人間性を失ってしまうものさえいる。ブリジットの場合、それは決定的な「記憶障害」として脳髄に焼きついた。彼女に許された「記憶」の容量は、あまりにも少ない。
彼女は、学院に入るまでの半生をまったく覚えていない。
彼女は、学院での生活のほとんどを覚えていない。
彼女は、自分がこの"砂の都"に移住することになった理由も覚えていないし、
世界が戦争状態にある理由も覚えていない。
それは生まれながらに、過去も未来も、黒く塗りつぶされているに等しい、神がかり的な虐待だった。
それでも、幾人かの巫女と同じように、生まれながらに壊れていれば、
彼女はここまで苦悩することもなかっただろう。
物心ついた時、ブリジットは、自らの脳に住まう"絵画"の中央で"貝殻の上に立つ裸婦"の、その圧倒的な存在感を、自身と無理やりに紐づけることで、死にかけた自我を蘇生させた。
その"絵画"こそが、"自分"であるという歪な錯覚。
人格の形成に必要な情報の全てを、足りない記憶に代わり、その"絵画"に頼ったのだ。
つまり彼女のナルシズムは、いわば精神的な防衛本能だ。
自らの肉体を晒し、世界中の賛意を集め、誕生を祝われるその姿。
彼女は、その脳裏に焼き付いた通りの、"美の女神"でいなければならないのだ。
彼女は、人の視線があるところでは明るく、そして優しく振る舞う。
"多くの他人に、好意的に受け入れられること"。
それもまた、"名画"の条件であるからだ。
自室に一人でいる間、ブリジットは空虚な面持ちで膝を抱いている。
衆目に晒されていない間、美術館の絵画が明かりを必要としないように。
彼女は薄暗い部屋で一人、次の"観客"が訪れる時を待っている。
だが時折―――、
今日のように冷え込んだ、砂のにおいが立ち込める月夜に限り。
彼女はランプを灯し、キャンパスの前で筆を執る。
学院にいた頃から、"知識"を復元するための技術として、彼女は絵画を学んでいた。
それは言語や常識と同様に、僅かな"脳の余白"へと詰め込んだ、彼女が持ちうる貴重な"記憶"のひとつだった。
…描けるものは、すべて拙い模倣に過ぎなかったが。
彼女の頬を、一筋の汗が流れる。
それは、白面に挑む恐怖の顕れだ。
この真っ白なキャンパスに、
模倣や再現ではなく、
脳裏に焼き付いた映像でもなく、
何か自らの内側から、
投影できるものはないだろうか。
それができれば、そこに描かれたものは、
もしかしたら…"本当の私"なのではないだろうか。
芸術を、為す―――、
自身の内側から―――、
どうにか、何かを、
ここに、どうにか―――、
―――、十秒、呼吸が止まる。
肺に飛び込んだ冷たい空気が、
消え入りかけていた意識を繋ぎとめる。
…むりだ。
できない。
沁みだした絶望が、
ランプの灯を吹き消した。
静寂の中で、あらゆる経験がすり抜けていった。
暗闇の底に、すべての"昨日"を取りこぼしていった。
機械的に記録できることと言えば、
己が今日、"そこにいた"という事実だけ。
昼間、学友と共に味わったはずの、あの料理の味さえ、もう思い出せない。
―――こんな役立たずの脳ミソで、一体どうやって、
ありもしない自分を、描き出せばいいのだろう。
そしてこんな夜を、もう何度繰り返してきただろう。
暗闇の中に筆を置き、
ブリジットはベッドに腰かける。
―――彼女は、この戦争が終わった後の進路を、既に決めている。
娯楽文化の豊かなディエクスに移住して、"舞台女優"になるべきだ、と。
常に衆目に晒される存在になれば、
そして己の中に、己ではない何者かを"役"として注ぎ続ければ。
この、がらんどうのような時間にも慣れるかも知れない。
ひどく歪んだこの自我にも、いつかは満足できるかも知れない、そう考えたからだ。
それは自己防衛本能から導き出された、合理的な判断だろう。
彼女の境遇を考えれば、最大限に前向きな思考でもある。
だが、それでも―――、
ブリジットはベッドから降りると、もう一度キャンパスに向かった。
砂を乗せた冷たい夜風が、かたかたと窓を叩く。
―――ランプの灯は消えてしまった。
だけど、今夜はまだここに立てる。
窓の向こうに輝く蒼白い月が、キャンパスを照らしてくれている。
日中の彼女は、このような表情を人に見せることはない。
それは不幸を嘆き、薄弱さを嫌い、だがそれすら忘れ、虚無に苦しみながら、
それでも立ち向かい続け、白紙の中に未だ知らぬ"己"を描き出そうとする、必死さであり、勇敢さだった。
ブリジットは筆を執り、
そして心に言い聞かせる。
色は白…あるいはきっと、この月光のような色がいい。
これだけは私の"本心"だ。
"あの絵画"は、誕生を、目覚めを、生命の朝を描いたもの。
ならばこそ、死を、眠りを、この夜を美しいと感じるこの心だけは、
きっとぜったいに、私自身のものなんだ。
ならば、できる。
私をこうしてキャンパスの前に立たせる、熱っぽい"なにか"。
覚えている限りのものから、
"それ"に輪郭を与えるんだ―――。
筆を握った右手が、ゆっくりとキャンパスに伸びる。
瞳に決意をたたえた彼女を、月明りが静かに照らしている。
そしてその横顔は、まるで絵画のように美しく―――。