
プロフィール
――用途不明の物質、ジスプロシウムの識者
年齢に比べて幼い言動が目立つ他、
突然に意味不明な単語を口走ったりもする、フシギ系の巫女。
良く言えば野性的であり、元気過ぎることが特徴。5秒以上はじっとしていられない。周りが喜べば自分も喜ぶ、周りが悲しめば自分も悲しむ、といった善性の純粋さを持ち、基本的な性格は底抜けに明るく、常に誰かと一緒にいることを好んでいる。
一見してそうは見えないが、年齢相応の、あるいはそれ以上の知性や感性を持ち合わせているらしく、言葉足らずに表現しようと努力する様が見られる。
その経歴は、かつて学院においてさえ再現、運用が困難とされた、
"異界の火"に関する知識を有した学徒巫女。
数年前まで学院の最奥区画に秘匿、封印されていたが、
ある時を境に「失踪」したことになっている。
"デイジー・ディー"という名前は身元を隠すための偽名であり、
学院に登録されている巫女名は「デューテリウム・ダブル」。
巫女寮を拠点としているが、商人への貸し出しは基本的に行われていない。
彼女の能力を活用するためには、様々な資格の取得と、ザントファルツ通商ギルドからの許可証が求められる。
一見して猫のようなエスティア人的特徴を有しているが、
その耳部は脳に、その尻尾は脊髄に、それぞれ接続されており、
彼女の不安定な生体龍脈(バイオタイド)を調整している装置である。
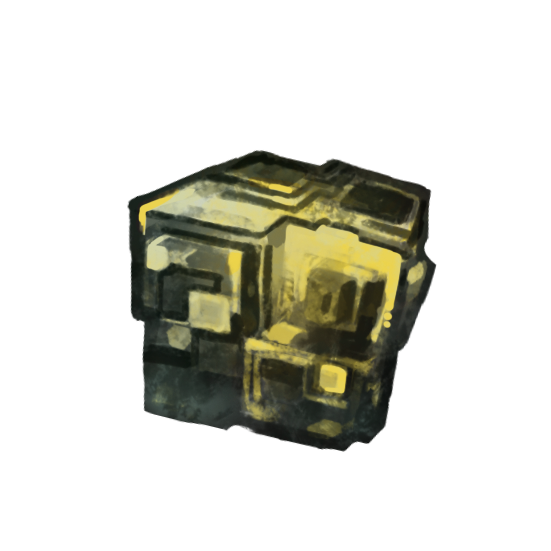
STORY
一枚の窓もない部屋。
未知の光源によって照らされた、
潔白の部屋に彼女はいた。
白い作務衣のようなものを着せられ、
木でも、石でもない椅子に座らされ、
その手と足は革縄で縛られ、
眼は覆われ、隠されている。
"デューテリウム・ダブル"。
作務衣に付けられたネームタグには、そう書かれていた。
地面を這う無数の透明なチューブが、
少女の全身に接続され、何かを送り続けている。
「やぁ、ディー・ディー。
気分はどう?」
誰かが、少女に声をかける。
その声は清水のように澄み、部屋に充溢していく。
静かな反響。
この部屋に、この二人以外の生物は存在しないように思えた。
動物はもちろん、
ヒトが未だその概念を知る由もない、極細の微生物さえも。
「…イマイチだな~。
ここは寒いし、渇いてて、キノコも育たない。」
少女からこぼれた言葉は、
緊縛された状況下とは思えないほど、頓狂だった。
「そう。
それじゃあ、今日も質問を始めていいかな?」
相対する人物の姿は、少女には見えない。
少女はここで幾日、幾月、幾年もの間、
質問に答えるだけの日々を過ごしている。
「…。」
少女は無言の肯定を示す。
拒絶は死だ。
"彼ら"にとって、
少女の自我など、ちっぽけなソフトウェアに過ぎない。
それが存在を許されているのは、
円滑な情報抽出のためだ。
必要でなくなれば、
それは消されるか、新たに造られるか、更新されるか。
いずれにせよ、
それが"己の死"であることを、少女は知っている。
「それじゃあ早速―――、」
突如として、少女の視界が開かれた。
幾日ぶりに見る光だ。
眼をしぱしぱと瞬かせる少女の前に立つ人物。
その影は、まだ眼に馴染まず、はっきりとしない。
だが、それより先に少女が認識したものは、
その人物の手に載せられた、黄色の物質であった。
「君は以前のテストで…この物質の、名前を呼んだらしいね?
それは、間違いない?」
「ジスプロシウム。」
情報は、少女の脳裏をついて出た。
質問されることに慣れ過ぎたのだろう。
人物の正体や、部屋の詳細や、自分の状態等、
他に知るべきことが山ほどあるにも関わらず、
少女は、質問の先を予測して答えた。
「この鉱石は…ジスプロシウムというのか?」
その人物の声色から、驚きが聴いて取れたことに対して、
少女は微笑んだ。
それは彼女にとっての、たった一つの娯楽だった。
―――"彼ら"の知りたいことは、
みな、私の脳裏からこぼれて落ちる。
そのしずくを"すくいあげよう"と、
必死に身を屈めて、
彼らは取りこぼさんとする。
―――滑稽だ。
「そうだよ~。でも鉱石じゃないな。惜しい。
正確には希土類元素(きどるいげんそ)だ。
ランラン、ランタノイドなのだな~。」
だから教えてやる。
彼らには決して理解できないであろう言葉で。
浴びせてやる。
誰の理解も届かない"それ"を。
ところが、この日は少し、様子が違った。
ジスプロシウムの欠片を手にした人物は、
額に指先をあてて、何かを思案している。
「… … キド、ルイ…元素。
類はタイプ…。
希土、希土類元素か。」
なるほど、とでも言うように、
僅かな笑みを湛えて、人物は続ける。
「やはりこれは、珍しいものか。それも"格別"に。
確かに、どんな地質からも、水脈からも、これの一部を含有するものはあれど、
"これそのもの"が採石された記録はない。
つまり、ジスプロジウム鉱石と呼ばれるものは、存在しない…のかな?」
少女は驚いた。
この人物は、昨日まで私に質問をしていた人間とは違う。
私の言葉を、響きのままに記述していた彼らとは違う。
少女の眼が光に慣れると、
その人物の姿が、ついに見て取れた。
…大人だ。
そして、綺麗な人だ。
学院の地上部にいた頃でさえ、
これほど端正に整った顔立ちを見たことはない。
そしてその瞳は、
まるで地表に降る途中の星の欠片。
夜天光の如き輝きを有していた。
少女は自分の眼に、保養が与えられたような感覚を得る。
今日、あるいは数日の間、
この人物の瞳の輝きを思い返すだけで、
無味なる時間の痛苦を退けられる、とさえ感じた。
人物は、そんな少女の心を知らないまま、さらに続ける。
「では、一言で教えて欲しい。
この合金は…"何の部品"だ?」
その答えは、少女の脳裏にあった。
完璧な答えだ。
人物が"合金"と言い当てたものは、
確かに部品だ。
だが、少女はその実態を形容する言葉を持たない。
代わりになるようなものを探して、並べることが精一杯だった。
「暖炉のレンガと、薪が一緒になったやつだな。」
「…暖炉?」
「そうだよ。暖炉のレンガだ。
考えてみろ~? 暖炉が木で出来てたらどうなる?
燃えるだろ~? だから暖炉のレンガだ、それは。
しかも薪なんだ。全部入れると、火が止まる。」
少女の説明は的を射ないものではあったが、
それが、彼女の発言し得るすべてだった。
少女は、この人物を煙に巻くつもりもなければ、
嘘偽るつもりもない。
「普通…逆じゃないかな?
薪を入れると、火は盛る。」
「逆か? そうだな。逆だ。
それは、そういう薪なのだな。
世の中には色々なニンゲンがいるだろ? 同じだ。
世の中には色々な薪があるのだ。アメイジング。」
その言葉を聞いて、
人物は再び、深い思想に耽る。
「…最後に質問を、もう一つだけ。」
もうひとつ?
あと、たったのひとつでいいのか?
口をついて出そうになった言葉を、
少女は諌めた。
何かが違う。
やはりこの人物は、
昨日までの学院の人間と決定的に異なる。
もしかすると―――、
もしかしたら―――、
少女は、最後の質問がどんなものであろうと、
出来る限り正確に答えようと決意した。
「君は、その暖炉の作り方を知っている?」
「知ってるよ。」
脳髄の流れに逆らって、
頭中を駆けるパルス幾条。
引きずり出された設計図を、
想うほどに言葉が足りない。
不正に歪んだ言葉の切れ端を、
集めて少女は紡ぎ出した。
それこそ学院最大の秘封、
彼女がこの地下実験棟に、
閉じ込められ続けている理由だった。
「そ…それは、な。わ、わかるよ。
わかるけど…すごく難しい。
かっ…紙とペンが、100個ずつくらい欲しいし、
その他にも、いろいろ、いろいろ必要だ。
ほんとにいろいろ。
多分、わたしたちみんなが、みんなで協力しないと、ダメ。」
「私たち? 学徒巫女たち、ということ?」
「そう、夏休みの、自由研究のような、気軽さでは、全部はムリ。
あ、頭…痛いから、ちょっと、待って。」
「…すまない、ディー・ディー。
君を苦しめるつもりはなかったんだ。
ありがとう。」
ちょっと待って。
まだもう少し喋らせて欲しい、と。
言おうとしたのに言葉がない。
奥のものを引っ張り出し過ぎたせいだ。
手前のものがなくなってしまった。
「質問はこれで終わりだ。」
「ま、待って。」
少女は繋がれた身をよじった。
しかし、投げかけられた言葉は、
少女にとって意外なものであり、
その人物にとっては、
自然なものだったようだ。
「君のために、私に何かできることはあるかい?」
その言葉を耳にした瞬間、
堰を切ったようにして、
言葉と涙が、少女から溢れていった。
「ここから出たい。外に出たい。
ここは寒いし、カラカラして、ぜんぜんダメ。
出たいんだ。みんなのところに帰りたい。
でもここは地下で、暗くて、
寒くて、学院だから、ぜんぜんダメ。
ダメだけど。」
―――ここから出たい。
以前と同じように、地上で暮らしたい。
仲間たちのところに戻りたい。
不可能なのはわかっている。
巫女は学院の資産だ。
世界にとっての資源だ。
彼らが自分を、解放することなど有り得ない。
アイエンティ最大の秘封であるこの場所に、
学院外部の人間がやって来ることも、有り得ない。
だけど―――、
必死に希望を繋ぎとめようとする少女の思考は、
生まれてから一度も聞いたことのないような轟音と、
それに伴う衝撃によって吹き飛ばされた。
思わず顔を背けるほど、
濁った風が部屋中に吹き荒ぶ。
それが収まり、少女が顔を向けた先、
星の瞳を持つ人物、その背後で、
"天井がぽっかりと口を開けていた"。
ああダメダメ。ここは滅菌室なのに。
一体何なんだ。誰なんだ。
学院の秘封を"台無し"にするような、この所業。
崩れた天井、その中から瓦礫を押し上げて現れたのは、
何だろう。あれは何だろう。形容が難しい。
ニンゲンだ。ニンゲンのように見えるが、
しかしその姿は、これまでに知るどれとも違う。
輝ける赤星、輝ける青星、輝ける緑星。
そのいずれにも見え、いずれとも異なる光の束を纏った戦士。
幼い頃に読んだ神話の物語が、
脳裏の奥底で閃いた。
そう、あれは…"騎士"だ。
星の瞳を持つ人物は、振り返ることなく肩をすくめ、
まるで咎めるようにしてその名を呼んだ。
「エレイン!
もう少し静かに。」
「申し訳ありません。
階層ごとに防衛戦力が配置されていたので、
"地表からここまで掘る"方が早いかと思いまして。」
「これなら最初からさぁ…」
誘拐した方が早かったよね―――、
と愚痴るように続け、星の瞳を持つ人物は、少女の緊縛された椅子に近づく。
そして、その周辺機器を、まるで手慣れたものであるかのようにして解除していった。
「驚かせてごめんね。
でも安心して。ディー・ディー。
私も彼女も味方だし、君の願いはきっと叶う。
移住先は、ザントファルツなんてどうだい?
あそこには、君の仲間もたくさんいる。」
唐突な"救い"の訪れに、
少女の頭は焼き切れるほどに混乱していた。
手足の戒めが解かれて尚、自分の脚で立つ方法を思い出せないでいる。
見かねて、星の瞳を持つ人物が、手を差し伸べた。
それに縋るようにして、握ろうとしたディー・ディーの身体が、
しかしその寸前で、ひょいと持ち上げられる。
"騎士"はまるで荷物を扱うかのようにして、
ディー・ディーの身体を担ぎ上げたのだった。
「よーし、そしたらもう、誘拐でいいか!」
快活に笑って部屋の穴を見上げる、星の瞳を持つ人物。
それにつられて顔を挙げた先、
地上から差し込んだ、一条の光が眩しい。
それは彼女が、もう二度と見られないと思っていたもの。
凍れる夜の、月の光だった。